睡眠時ブラキシズム(歯ぎしり)
睡眠時ブラキシズムとは?〜夜の破壊活動の始まり〜

「ブラキシズム (Bruxism)」とは、睡眠中に無意識に行われる「歯ぎしり」や「噛みしめ(食いしばり)」といった、異常な口腔習癖の総称です。
「朝起きると、顎が疲れている」
「頭痛がする」
「歯が削れてきた」
これらのサインは、眠っている間にお口の中で「破壊活動」が繰り広げられているサインかもしれません。
ブラキシズムの3つのタイプ
ブラキシズムは、その動きによって主に3つのタイプに分類されます。
グラインディング(歯ぎしり)
上下の歯を強くこすり合わせる横方向の動きです。
一般的に「ギリギリ」という音を伴います。
クレンチング(噛みしめ・食いしばり)
上下の歯を強く噛み締める垂直方向の動きです。
音は出ませんが、歯や顎関節に最も強い圧力をかけます。
タッピング(カチカチ)
上下の歯をリズミカルにぶつけ合う動きです。
特にクレンチング(噛みしめ)は音が出ないため、本人はもちろん、隣で寝ている家族も気づきにくく、静かに、しかし確実に歯と顎を蝕んでいく「サイレントキラー」とも呼ばれています。
体重の何倍もの力が加わる夜
私たちが日中に食べ物を噛む力は、通常、体重の半分程度です。
しかし、睡眠中のブラキシズムは、無意識で抑制が効かないため、その力は体重の2〜10倍、最大で100kg以上にもなると言われています。
この極端な力が、一晩のうちに数時間にもわたって歯や顎関節に繰り返し加わることで、様々な深刻な問題を引き起こします。
あなたの顎と歯のSOSサイン:ブラキシズムが引き起こす症状
ブラキシズムは、口腔内だけに留まらず、全身に影響を及ぼします。
以下の症状に心当たりのある方は、今すぐ専門的な検査が必要です。
口腔内のサイン(歯と歯周組織の異常)

異常な歯のすり減り(咬耗)
歯ぎしりにより、歯の表面のエナメル質が削れ、象牙質が露出する。知覚過敏の原因にもなります。
歯のひび割れ・破折
強い噛みしめ圧により、歯に目に見えないヒビ(クラック)が入り、進行すると歯が割れてしまいます。
詰め物・かぶせ物の頻繁な破損
修復物に過剰な力がかかることで、セラミックなどが欠けたり、詰め物が外れたりします。
歯周病の悪化
歯周病にかかっている歯に異常な力が加わることで、歯を支える骨の破壊が加速します。
骨隆起(こつりゅうき)
噛みしめ圧に耐えるため、歯を支える骨が異常に発達し、顎の骨が盛り上がって硬いコブ(骨隆起)ができることがあります。
顎・筋肉・全身のサイン(痛みと疲労)

起床時の顎、筋肉の痛みや疲労感
睡眠中の異常な筋活動(クレンチング)により、顎を動かす咬筋や側頭筋が過度に緊張し、疲労・炎症を起こしている状態です。
起床時の頭痛
側頭筋や後頭部の筋肉の強い緊張が原因で、緊張型頭痛を引き起こします。
起床時に口が少ししか開かない(開口障害)
顎関節への過度な負担や、筋肉の硬直による症状です。
頬の内側の粘膜に噛みしめ線
睡眠中に頬の粘膜を歯で持続的に圧迫しているサインです。
舌の側面に歯の圧痕(ギザギザの跡)
睡眠中に舌を強く歯に押し付けている(噛み込んでいる)サインです。
なぜブラキシズムは起こるのか?〜ストレスと睡眠の深い関係〜
ブラキシズムの正確な原因は一つに特定されていませんが、最新の研究では「脳と睡眠のメカニズム」に深く関わっていることが分かっています。
1. ストレスと心理的要因

仕事や人間関係、社会生活からくる心理的なストレスは、ブラキシズムの発生頻度と強度を上げる主要な引き金です。
ストレスが高まると、睡眠中も脳が完全に休まらず、自律神経系の活動が活発化し、これが顎の筋肉に伝わって異常な運動を引き起こします。
2. 睡眠の質と脳の覚醒反応
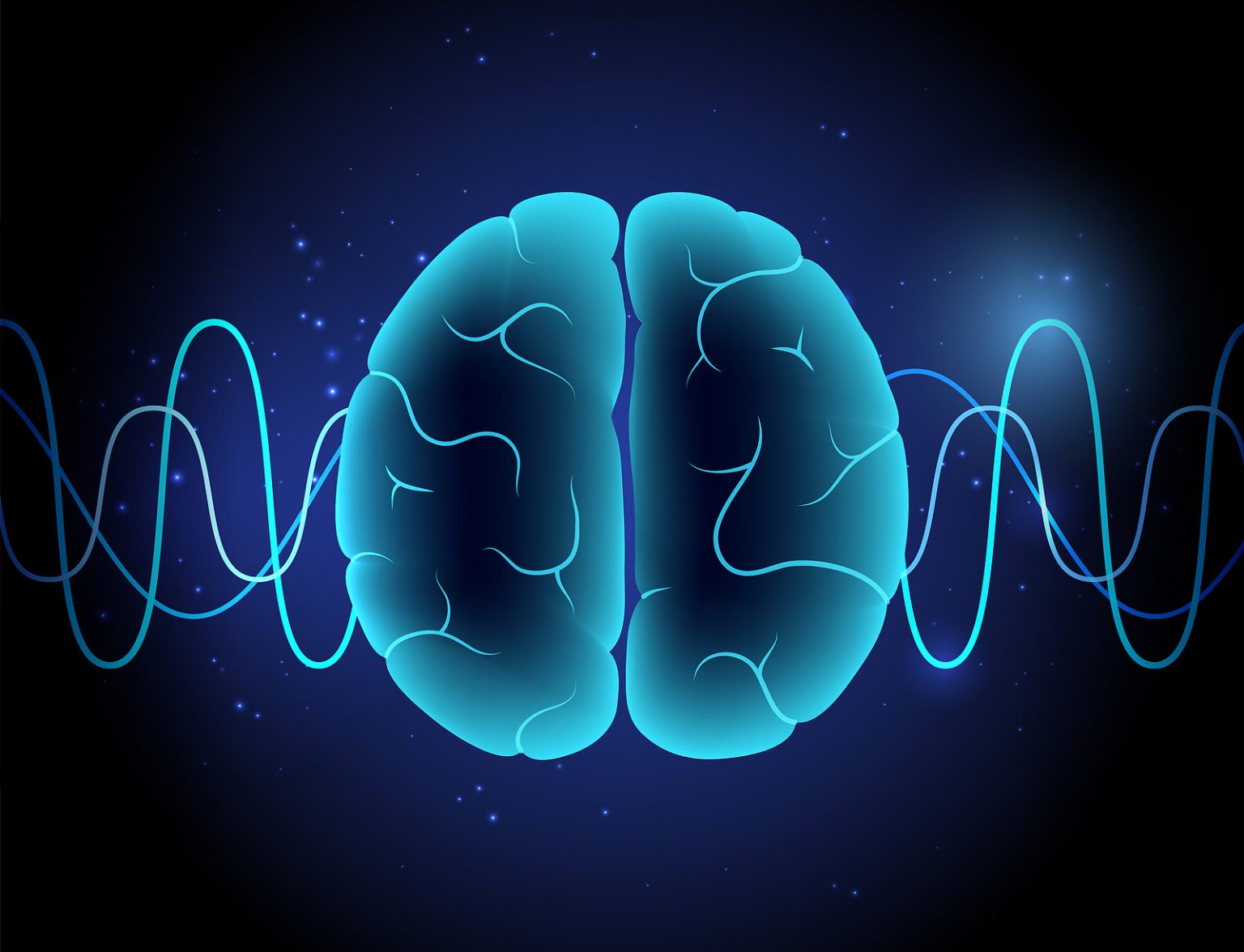
ブラキシズムは、睡眠が浅くなる瞬間(微小覚醒)に最も多く発生します。
覚醒に移行する際、脳は一時的に興奮状態になり、その一連の流れの中でブラキシズムが誘発されます。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)や周期性四肢運動障害といった睡眠障害を抱えている方は、頻繁に微小覚醒が起こるため、ブラキシズムの発生リスクも高まります。
3. 口腔内の要因

極端に高い詰め物やかぶせ物、または不安定な噛み合わせが、ブラキシズムの引き金となることがあります。
また、ブラキシズムの傾向は、遺伝として家族内で受け継がれる可能性が指摘されています。
科学の目による診断:睡眠筋電計が解き明かす真実

高輪歯科では、ブラキシズムの経験や勘に基づく治療ではなく、科学的根拠(EBM)に基づいた診断を徹底しています。
そのために不可欠なのが、ウェアラブル筋電計を用いた睡眠筋電計検査です。
ブラキシズムは、診療室ではほとんど発生しません。
だからこそ、ご自宅で、普段通りにお休みいただいている状態を計測することが重要です。
ウェアラブル筋電計は、診療室ではわかりにくい睡眠時のブラキシズム(歯ぎしり、噛みしめなど顎の動きと歯の接触に関連する障害)を客観的に「見える化」することができる機器です。
筋電計でわかること
筋電計は、顎を動かす筋肉(咬筋、側頭筋など)の活動によって発生する電気信号(筋電図:EMG)を記録します。
力の強さ(筋活動レベル)
発生した力のピーク値や、持続的な力の平均値。日中の噛む力と比較し、どれほど異常な力が加わっているかを特定します。
ブラキシズムの頻度と回数
一晩に何回、どれくらいの頻度でブラキシズムが発生しているかを正確に把握します。
発生パターン
歯ぎしり(グラインディング)が主体なのか、噛みしめ(クレンチング)が主体なのかを分析し、最適な治療法を選択する判断材料とします。
持続時間
一回のブラキシズムがどれくらいの時間続いているかを調べます。
睡眠時ブラキシズムの具体的な治療法:高輪歯科のアプローチ
筋電計による精密な診断を経て、高輪歯科では、患者様のブラキシズムの程度、原因、ライフスタイルを考慮し、複数のアプローチを組み合わせた最適な治療を提供します。
ナイトガード(マウスピース)

最も一般的な治療法です。睡眠中に装着することで、以下の効果が期待されます。
歯の保護
歯同士の直接的な接触を防ぎ、すり減りや破折から歯を守ります。
顎関節の負担軽減
顎の位置を安定させ、関節への衝撃を緩和します。
力の分散
咬む力をマウスピース全体で受け止め、特定の歯や部位への集中を避けます。
ボトックス(薬物療法)

筋電計で極めて強い噛みしめ力が計測され、ナイトガードでも顎や筋肉の痛みが改善しない重症例に対しては、ボツリヌス毒素製剤(ボトックス)を用いた治療を検討する場合があります。
顎の筋肉(咬筋など)に注射することで、筋肉の過剰な働きを一時的に抑制し、ブラキシズムの力を弱める効果が期待されます。
顎の痛みや頭痛が深刻な場合に、顎への負担を急激に減らす目的で用いられます。
口腔漢方処方

ブラキシズムの原因の一つに、ストレスや自律神経の乱れが深く関わっています。
身体の状態を整え、睡眠の質を高めることで、夜間の異常な筋活動を鎮静化する目的で、漢方薬の処方を検討する場合があります。
身体に優しく、根本的な体質改善を目指す治療法の一つです。

